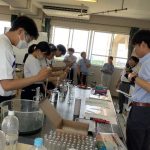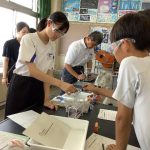令和7年度 一斉研修会を開催しました。
6月19日(木)に市内18会場で「一斉研修会」を開催しました。どの会場においても、「主体的・対話的で深い学び」につながる提案授業がなされました。授業後に行った研究協議会では、学びを深める手立てや教師支援の在り方、個に応じた支援の在り方などを協議し、授業記録をもとに建設的で真摯な討論がなされました。
各部会の専門性が発揮される一斉研修会は、私たちにとっても学びの多い、価値ある行事となりました。
国語
学年:中学校・1年 教科:国語
思いを語る比喩『星の花が降る頃に』
本単元の導入では、小説「君の名は。」を取り上げ、魅力的な比喩表現に出会わせました。その出会いをもとに「星の花が降る頃に」でも、比喩表現による効果について注目していくことで、読みを深めていきました。また、登場人物の繊細な気持ちを表現し、情景に臨場感を与える、そんな比喩表現の効果を、協働的に作品を読み進める中で実感していきました。本時では「場面の様子や登場人物の心情がより強く伝わってくる表現はどれか」と生徒に問いかけることで、場面の様子や登場人物の心情の理解を深めていきました。また、比喩表現を使わない描写を提示し、どちらの方が分かりやすいか立場を選択させることで、生徒が主体的に動き出す姿が見られました。単元の終末では、習得した学びを活用し、自ら比喩表現を使って、登場人物の心情や情景をいきいきと表現する姿も見られました。
社会
学年:小学校・6年 教科:社会
よみとけ!物が語るむかしの物語 ~縄文・弥生・古墳へ
社会科歴史的分野の学習として、縄文・弥生・古墳時代の遺跡や出土品などの「もの」を通して時代の様子や変化を読み解き、変化の理由を考察する授業を行いました。本時では、授業会場を歴史博物館に設定したり、歴史博物館職員の方がゲストティーチャーとして参加したりする活動を通して、実物に触れる感動を味わいながら、自分の考えを深めることができました。また、身近な地域の歴史を学習することを通して、歴史に興味・関心をもって、よりよい社会づくりへの参画しようと意識や意欲を高める姿が見られました。
算数・数学
学年:中学校・1年 教科:数学
「世界最大のハチの巣を作ろう」~文字の式~
前時までにハチの巣の構造を知ったり、世界最大のハチの巣の層数がいくつあるのかを求めたりしていました。
本時では、各層の部屋数の求め方を追究しました。これまでの学習で調べたことや分かったことを基に、地道に数える方法や、n層までの部屋の総数からn−1層前までの層数を引いて求める方法、文字を使って立式することで求める方法等が出てきました。生徒が自分なりの考えをもち、それを伝えることで、「主体的・対話的で深い学び」を基に、数学的な見方・考え方を働かせた学びの実現を目指しました。
理科
学年:中学校・3年 教科:理科
酸・アルカリとイオン―万能指示薬を作って透明な液体を区別しよう―
化学変化について、見通しをもって実験を行い、イオンと関連付けてその結果を分析、解釈しました。科学的に探究する活動を通して、化学変化における規則性や関連性を表現したり、課題を解決したりする力を養いました。
これまで、透明な水溶液を解き明かすことを目標に実験を重ねていました。本時では、そんな水溶液を解き明かす万能指示薬の完成に向け、これまでの実験結果を基に、量的な視点をもって追究を深める姿を目指しました。また、各班の実験状況をリアルタイムで共有できる環境をつくることで、級友とかかわり合いながら学び合いができるような授業を展開しました。
生活
学年:小学校・1年 教科:生活
あそびにんぽう パワーアップ~スイカさんとたのしくあそぼう!~
安城北部小学校の1年生は、扉のない開放的な教室、昔遊びコーナーのある廊下、グループ隊形の座席といった環境で生活しています。これらは、幼保小の接続を大切にするスタートカリキュラムの要素を取り入れたものです。単元づくりにおいても遊びの要素を意識した忍者の設定、学校探検や遊びづくりなどの体験活動を重視しています。
本単元では、学校探検で見つけた隣接する保育園の年長児と遊びたいという願いの実現に向けて、遊びづくりに没入していきました。忍者の修行として運動遊びやおもちゃづくりを体験する中で、得た気付きを「飛び出しの術」「転がりの術」などと価値付け、共有してきました。本時では、個を軸とした主体的な遊びづくりの中に、タブレットを活用して互いの遊びを広めたり、「忍法お助けの術」で友達と関わる場を設定したりしました。これまで積み上げてきた学びや友達の考えを生かし、工夫する姿が見られました。
造形
学年:小学校・6年 教科:図画工作
のぞいて広がる私の未来
未来の自分の前に広がる光景を想像し、一面または二面の壁がある厚紙上に紙粘土や画用紙などのさまざまな素材を使って表しました。厚紙のどこかに、針金で作る輪を自分の視点として設置しました。本時では、グループや全体でこだわりや困り感を共有することで、針金から見える光景を自分の表したい瞬間に近づけていく児童の姿が見られました。
音楽
学年:中学校・2年 教科:音楽
目指せ声楽家!カンツォーネの歌い方の研究をしよう~サンタルチア~
本題材では、音楽の要素に注目しながら、曲にふさわしい歌唱表現を創意工夫する力を育みました。導入ではプロの歌声に触れ、「カンツォーネらしく歌うにはどうすればよいか」を考えるきっかけをつくりました。本時では、各グループが表現するうえで意識したい「推しポイント」を設定し、目標をもって練習しました。異なる困り感をもつグループの声を取り上げて語らせることで、多様な視点からの工夫が生まれました。個人で考えたり、グループで意見を出し合ったりしながら自分の考えを明確にし、他者の意見を取り入れて試行錯誤しながら歌唱活動に取り組む姿が見られました。
体育
学年:小学校・4年 教科:体育
CDTV~4年梅組のダンス!ライブ!
【C】チャレンジ【D】ダンシング【T】チームワーク【V】ビクトリー
本単元では、児童の創造力や独創性を伸ばすことをねらいに、音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」をヒントにした活動を取り入れた表現運動を行いました。自分たちで好きな曲を選び、振付を創作することで、仲間と協働しながら即興的に表現する喜びを味わいました。また、本校の「東部小授業探求モデル」に基づき、見通す・協働・振り返りの流れを通じて、学びに一貫性と深まりをもたせました。子どもたちの「もっとやりたい!」という思いが引き出され、自信をもち、表現の幅を広げていく姿が見られました。
技術・家庭
学年:小学校・6年 教科:家庭科
それ、本当にきれい? ~自分たちの掃除、見直してみよう~
6年生の児童は、1年生の清掃活動を手伝う中で、「教えているのに教室がきれいにならない」という疑問にぶつかりました。そこから、自分たちの清掃の仕方を問い直し、より効果的な清掃方法について考える学習が始まりました。本時では、グループごとに試行錯誤を重ねた清掃方法をふり返り、他グループの実践と比べることで、自分たちの掃除をさらにアップデートしようとする姿を引き出しました。清掃のやり方・道具・効率の3つの視点から改善に取り組むことで、生活をよりよくする力が協働の中で育まれていくことを実感できる授業を目指しました。
英語(外国語活動)
学年:小学校・3年 教科:英語
好きな色を尋ね合って、~My Butterflyを作ろう~
本実践では、色や食べ物、スポーツなどについて自分の好みを伝えたり、相手に好きかどうかを尋ねたりする活動を行いました。単元を通して、幼虫が色とりどりのチョウになる絵本の英語による読み聞かせを行い、英語表現に自然に慣れ親しむことができるようにしました。単元の最後には、絵本からつなげてMy Butterfly作りを行いました。本時では、Do you like~?を使って、相手の好きな色を聞いたり、自分の好きな色を答えたりして、My Butterfly作りの材料カードを集める活動を行うことで、積極的に好きなものを伝え合うことができるようにしたいと考えました。HRTやALTのリアクションや声かけによって、自信をもって積極的に英語を使おうとする姿が見られました。
道徳
学年:小学校・4年 教科:道徳
正しいことを行うために
「スーパーモンスターカード」という教材を用いて、正しいことを行うために大切なことを考えました。心情を視覚的にとらえるために教具「心の数直線」を用いて、登場人物の葛藤に注目しました。また、話には登場しない状況を設定したり、他にもっと良いタイミングがなかったかと問い返したりすることで、さまざまな角度から登場人物の心情をとらえました。児童が話し合いを通じて、勇気をだして自身が正しいと思うことを行動に移していきたいという思いを高める姿が見られました。
特別活動
学年:小学校・4年 教科:学活
2年生と仲良し大作戦
本単元では、縦割り活動を行う中で生じる課題を、クラス会議を通して話し合っていきました。解決策を話し合い、合意形成し合う経験を重ねることで課題を自分のこととして捉える意識を高めました。本時では、児童主体で、「2年生と仲良し大作戦を成功させるには、どうすればよいだろう」という議題に対しての話し合いを進めていきました。話し合いが停滞したり、意見に偏りが見られたりする際には、「自分が2年生だったら、どうしてもらえたらうれしいか」と教師が問いかけることで、相手目線になって考えられるようにしました。決定した解決策を選んだ理由を聞いたり、よさを取り上げたりすることで、相手を思いやることの大切さについて考えを深める児童の姿が見られました。
総合学習
学年:小学校・6年 教科:総合
つなごう!桜井の未来~安城一番 桜井の一番~
桜井には魅力的な歴史や文化、町づくりがあるが、特に桜井凧を取り上げました。桜井凧に関わる方々の思いに触れたり、実際に凧を作り、揚げる活動を行ったりして、地域の魅力について再発見し、地域の一員として自分たちにできることを考え、発信する姿につなげていきました。本時では、学級の話し合いを通して、桜井凧に関わる方の思いを振り返ったり、自分たちの桜井凧への思いを語ったりすることで、桜井凧への思いや今後の活動への意欲を高めることができました。
特別支援教育
学年:小学校・特別支援学級 教科:自立活動
聞き名人になろう
単元を通して、聞く力の基礎となる「相手の目を見る、最後まで聞く」といった聞き方のポイントを黒板に掲示することで、児童がこれまで積み重ねてきた聞くスキルを継続して取り組めるようにしました。また、個に合わせためあてを設定し、黒板に掲示することで、本時で身に付けたい力を意識して振り返りに生かしました。
「先生たちからのお願いを聞いて、おつかいを成功させよう」では、ペアでおつかいを成功させるために個でつけた聞く力とコミュニケーションの力を使いながら活動を行いました。児童が主体的に取り組めるおつかい活動の設定の工夫、発達段階に合わせたメモ用紙、絵カードの支援を通して、児童たちは、聞き取ったことをメモに書きました。メモを頼りに品物を選んだり、ペアの児童や先生に聞いたりしながらおつかいをすることで、日常生活に生かせる力を育んでいきました。
図書館教育
年間を見通した図書館教育
今年度の重点項目の一つである「学校図書館を利用した授業実践」を推進するために、図書の活用や学校司書・図書情報館との連携を意識した授業について、学校司書や図書情報館職員も交えて協議を行いました。小学校は国語科、中学校は担当の専門教科について、年間を見通して、身につけさせたい情報活用スキルを系統的に示したり、日常的に図書と関わることができる環境をデザインしたり、児童生徒の学習活動や読書活動をサポートする方法について考えました。
養護
学年:中学校・2年 教科:保健体育
生き生き 長生き みんなで元気!~「健康な生活と病気の予防」~
人生100年時代を生きていく子どもたちには、生活習慣病やがんについて正しく理解したうえで、健康で長生きするための方法について考え、行動できるようになってほしいと思います。日本人の2人に1人がかかるといわれているがん。しかし、日本はがん検診の受診率が低いという実態があります。そこで、「がん検診の受診を迷っている学級担任」という架空の設定の中で、どのように説得していくとよいのかを考える活動を行いました。前時までに得た知識や自分の意見を友達と聴き合うことで考えを深め、自分の言葉でがん検診の大切さを伝えました。がんはだれにでも発症しうる病気であることに気付き、自分のこととして生活習慣を見直したり、身近な人に予防方法や早期発見の大切さについて伝えたりすることができる姿が見られました。
情報教育
学年:小学校・5年 教科:算数
小数のわり算〜自分で考えみんなで深めよう〜
小数のかけ算を学ぶ単元において、自律的な学習者を育成することを目指しました。本時では、小数のかけ算の概念的理解を深めるため、作問演習を行いました。ミライシードのオクリンクプラスを活用することで、児童は学習目標や振り返りを蓄積し、自己調整をしながら学びを進めていきました。さらに、作問した問題を説明し合う場面や、グループで解法の比較・検討を行うことで思考を深め、理解の定着を図りました。タブレットの活用を通じて、児童が主体的に学びを進める姿が見られました。
学校事務
デジタルで生まれ変わる安城の教育環境
教育環境の向上を実現するためには、財務、文書管理、情報管理等の学校運営全体におけるDX推進が不可欠です。
県政お届け講座「愛知県のDX推進 ~デジタルで生まれ変わる愛知~」の内容をもとに、5年後、10年後の安城市をイメージしながら「デジタルで生まれ変わる安城の教育環境」について自由に考え協議しました。今後の研究活動の方向性を定めるための手がかりとなりました。